ワライタケとは

ワライタケ(笑茸、学名: Panaeolus papilionaceus)は、ヒカゲタケ科ヒカゲタケ属に分類される小型のキノコです。その名前は、このキノコに含まれる毒成分を摂取することで、酩酊状態や幻覚、あるいは笑い発作などの精神作用を伴う中毒症状を引き起こすことが由来になっています。
傘の直径は2〜4cm程度で色は灰色から灰褐色になる場合や黄色を帯びた白色になる場合があります。柄は細くなっていて長さは5〜10cm程度と小型のキノコです。

ワライタケのヒダ
ひだ(褶)は灰色から黒色で、成熟すると胞子の色により真っ黒に見えます。
キノコは栄養の取り方から大きく2つに分けることができます。一つは生きた生物にくっついて、そこから栄養を吸収する「寄生菌」、もう一つは生物遺体や排泄物、もしくはそれらが分解して生じたデトリタスなどを栄養源として生活する「腐生菌」です。
ワライタケは動物の糞や肥沃な土地に発生する腐生菌であるため、食べられる機会は少なかったと考えられますが、幻覚作用を有するシロシビン(Psilocybin)というアルカロイド系の毒成分を含有していることから広く知られるようになりました。
シロシビンを含有するキノコとしてシビレタケ属のキノコがあり、それらのキノコと比較するとワライタケは毒成分の含有量が少ないとされていますが、摂取量によっては十分な中毒症状を引き起こす危険性があります。
分布・発生環境

ワライタケはその生育環境の特性から世界中に広く分布しており、日本においても全国各地で発生が報告されています。
ワライタケは、主に動物の糞(特に馬や牛の糞)、または有機物が多く肥えた草地、牧草地、庭園などに発生します。かつて牛馬の放牧地であった場所や、公園の芝生、堆肥が使われた場所などで見られることがあります。
腐敗した有機物を分解して栄養を得る腐生菌であるため、動物の糞や腐植質が多い土壌で主に発生し、発生時期は主に春から秋にかけての温暖で湿度の高い時期です。
このような発生環境から、他の食用キノコを探している際に誤って採集されるというリスクは比較的低いとされますが、後述するように法規制の対象となっているため見つけた際の対応など注意が必要です。
ワライタケの毒
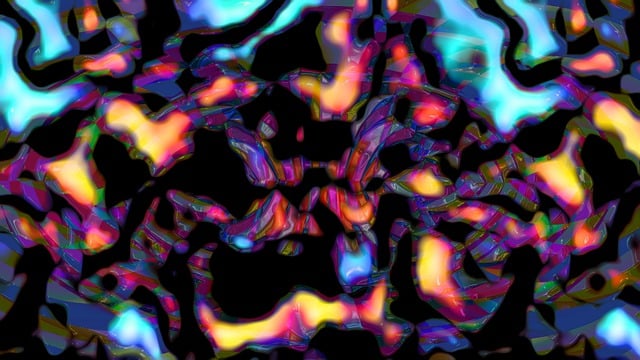
ワライタケに含まれる有毒成分の中で特に幻覚作用のある成分は、シロシビン(Psilocybin)と、その分解生成物であるシロシン(Psilocin)です。
これら成分は、脳内のセロトニン受容体に作用することで、幻覚や酩酊、意識の変容といった精神作用を引き起こします。
その他の成分として、コリン、アセチルコリン、5-ヒドロキシトリプタミンといった成分も含まれていると報告されていますが、主要な中毒症状を引き起こすのはシロシビンおよびシロシンであるとされています。
摂取後、通常は30分から1時間程度で幻覚(視覚、聴覚の変容)、多幸感(ハイな気分)、時間感覚の喪失、自己の意識の変化、酩酊状態などの症状が現れます。
また、このような精神的な症状の他、軽度の吐き気、嘔吐、動悸、めまい、血圧の上昇、瞳孔散大(散瞳)などの身体的な症状が現れることがあります。
過剰に摂取した場合や体質によっては、セロトニン症候群(中枢神経系の興奮、発熱、意識障害など)を引き起こす可能性があり、これが重篤化すると生命を脅かす危険性があります。
ただし、ワライタケは他のシロシビン含有キノコよりは毒成分が少ないため、重篤な状態に陥る例は比較的少ないと考えられますが、多量に摂取してしまった場合には非常に危険です。
シロシビンは、加熱しても失活しないことが特徴の一つです。このため、加熱調理しても毒性が失われることはありません。
ワライタケに含まれる毒の量と中毒になる量

ワライタケに含まれるシロシビンの含有量および人間に対する中毒量は、以下の通り報告されています。
-
中毒を引き起こす最小量:
-
ヒトに対する最小中毒量は、体重1kgあたり0.057mgであると報告されている文献があります。
-
これに基づくと、体重50kgの成人では約2.85mgのシロシビンで中毒症状が発症すると推定されます。
-
-
一般的な中毒量:
-
ヒトでの中毒量は、シロシビンとして5~10mgとされている文献もあります。ただし、その吸収率、摂取許容量、体内での動態などは不明です。
-
-
ワライタケの子実体に含まれる量(事例報告):
-
過去の沖縄での食中毒事例の報告によると、採取されたワライタケ(キノコ9個、総重量8.8g)に含まれるシロシビンは、4.1~4.7mgと推定されています。
-
滋賀県で採取された別事例のワライタケでは、乾燥重量あたり0.04%~0.05%のシロシビン含有量であったことが報告されています。
-
これらの報告から、ワライタケはわずか数本を摂取するだけでも、中毒症状を引き起こすのに十分なシロシビンを含んでいることがわかります。また、シロシビンの含有量は、キノコの発生地域や生育条件、個体差などによって変わることが考えらます。
法律による規制

ワライタケは、その幻覚作用を持つ毒成分シロシビンを含有しているため、日本では法律によって厳しく規制されています。
2002年(平成14年)に、ワライタケを含むシロシビンを含有するキノコが、麻薬原料植物として、麻薬及び向精神薬取締法において指定されました。
シロシビンは麻薬に指定されており、シロシビンを含有するワライタケの子実体(キノコ本体)も同法の規制対象となります。
そのため、栽培、所持、譲渡(売買)、使用など、これらすべてが法律で禁止されており、また、故意に採取したり、所持したりした場合、麻向法違反として厳罰の対象となります。
もしもワライタケのようなシロシビン含有キノコを発見した場合は、採集してはならず、速やかに保健所や警察署に届け出なくてはなりません。これは、麻薬成分を含む危険な植物・菌類が野外に放置されることを防ぐためです。
この法律による規制は、ワライタケが単なる有毒キノコであるというだけでなく、向精神作用を持つ麻薬成分を含んでいるという事実に基づいています。
まとめ
ワライタケ(Panaeolus papilionaceus)は、動物の糞や肥沃な土地に発生する小型のキノコです。
その和名は、摂取による笑い発作などの精神作用に由来しており、主な毒成分は強力な幻覚作用を持つシロシビンとシロシンというアルカロイドです。
これらの毒は脳内のセロトニン受容体に作用し、幻覚、酩酊、時間感覚の喪失といった中毒症状を引き起こします。わずか数本の子実体でも中毒量(シロシビン約2.85mg以上と推定)に達する危険性があります。
このシロシビンは麻薬に指定されているため、日本では2002年に麻薬及び向精神薬取締法により、ワライタケの栽培、所持、売買、使用などが厳しく禁止されています。
ワライタケを発見した場合は、触れずに速やかに保健所や警察に届け出ることが推奨されています。


![ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! ~ブルーレイシリーズ4~ 浜田・山崎・田中 絶対笑ってはいけない温泉宿1泊2日の旅 in 湯河原【Blu-ray】 [ ダウンタウン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7135/4571487557135.jpg?_ex=128x128)



コメント