タランチュラとは?

世界最大のクモ「ゴライアスバードイーター」
Photograph by Ryan Somma
タランチュラは、クモ綱クモ目オオツチグモ科に属する大型のクモの総称で、世界には1,000種以上が知られていて、一部の種類はペットとして人気があります。
タランチュラの中でも最も大きな種であるゴライアスバードイーター(Theraphosa blondi)は、脚を広げた長さが20cm以上、体重は170g以上にもなります。

後部に刺激性のある毛を持つ種類もいる
タランチュラはアリなどに噛みつかれないようにするため、全身が長い毛で覆われているだけでなく、種類によっては「刺激毛」と呼ばれる毛を後部に持っており、身の危険を感じると後脚で擦り飛ばして敵を追い払う防御行動をとります。
この刺激毛が目に入ったり、皮膚に付着したりすると、かゆみや炎症を引き起こすことがあります。
他のクモのように網を張って獲物を捕らえることはほとんどなく、待ち伏せや奇襲によって獲物を捕食します。獲物は主に昆虫や小型の爬虫類、両生類ですが、大型の種では小型の哺乳類や鳥類を捕食することもあります。
一般的にタランチュラは臆病な性格であり、人間を積極的に襲うことはありませんが、危険が迫ると刺激毛を飛ばしたり、威嚇のために体を持ち上げたりしますが、それでも効果がない場合に初めて噛みつくことがあります。
主な生息地・生息環境

タランチュラは、主に熱帯から亜熱帯にかけての温暖な地域に広く分布していおり、その生息地は北米南部から中南米、アフリカ、アジア、ヨーロッパ南部、オーストラリアなど、世界中に及びます。
生息環境は種によって様々ですが、大きく分けて以下の三つのタイプに分類されます。
-
地中性(Burrowers): 地中に穴を掘って生活するタイプで、タランチュラの多くがこのタイプに分類されます。穴の中は外敵から身を守る安全な場所であり、湿度や温度を保つことができます。
-
樹上性(Arboreals): 木の上や枝の間、樹洞などに巣を作り生活するタイプで、このタイプは脚が細く、木の上での移動に適した体型をしています。
-
地表性(Terrestrials): 地表に隠れ家を作ったり、落ち葉の下などに潜んだりして生活するタイプで、地中性と異なり深い穴を掘ることはありません。
これらの生息環境の違いは、タランチュラの形態や行動にも影響を与えていて、地中性のタランチュラは頑丈な体と短い脚を持つことが多く、樹上性のタランチュラは素早い動きと長い脚を持つことが多いです。
ちなみに、日本にタランチュラは生息していません。
タランチュラの4つの分類

タランチュラは、生息環境や地理的分布によっていくつかのグループに分類されることがあります。ここでは、一般的に用いられる分類方法に基づき、代表的な4つのグループを紹介します。
ツリースパイダー

Poecilotheria regalis
ツリースパイダーは、その名の通り樹上で生活するタランチュラのグループです。樹洞、木の葉の間、樹皮の隙間などに糸を張って巣を作り、獲物を待ち伏せします。
-
特徴:
-
細く長い脚を持ち、木の上を素早く移動するのに適した体型をしています。
-
警戒心が強く、非常に素早い動きで威嚇や逃走を行います。
-
地上性や地中性のタランチュラと比べて、毒性が強い種が多いと推測されていますが、これには個体差や種差があります。
-
一部の種は、鮮やかな体色を持つことがあり、ペットとして人気があります。
-
-
代表的な種:
- アビキュラリア属(Avicularia): 通称「ピンクマウス」などと呼ばれる南米に生息する樹上性のタランチュラ。
- ポエキロテリア属(Poecilotheria): インドやスリランカに生息し、美しい模様を持つ種が多いです。
バードイーター

Grammostola pulchra
Photograph by Leandro Malta Borges
バードイーター(Bird eater)は、南米に生息するタランチュラのグループで、世界最大級の大きさを誇る種が多く含まれます。名前の由来は、大型の種が鳥を捕食する様子が観察されたことにありますが、彼らの主食は主に昆虫や小型の脊椎動物です。
-
特徴:
-
非常に大型で、重厚な体型をしています。
-
刺激毛を持つ種が多く、危険を感じると刺激毛を飛ばして身を守ります。
-
地表性または地中性の生活を送ることが多いです。
-
比較的穏やかな性格の種が多いですが、攻撃的な種も存在します。
-
-
代表的な種:
- ゴライアスバードイーター(Theraphosa blondi): 世界最大のタランチュラとして知られ、脚を広げた長さが30cm近くになります。
- ブラジリアンブラック(Grammostola pulchra): 美しい漆黒の体色を持つ人気のペット種です。
バブーンスパイダー(バブーンタランチュラ)

Pelinobius muticus
Photograph by Tracy Pirie
バブーンスパイダー(Baboon spider)は、アフリカ大陸に生息するタランチュラのグループです。その名前は、サルのような毛深さと、脚の裏側の指先にある毛の房が、サルの指に似ていることに由来すると考えられています。
-
特徴:
-
他のタランチュラと比べて、脚が太く、がっしりとした体型をしています。
-
刺激毛を持たない種がほとんどであり、防御は噛みつきや威嚇が中心となります。
-
警戒心が強く、動きが素早いため、取り扱いには注意が必要です。
-
地中性または地表性の生活を送ることが多いです。
-
-
代表的な種:
-
キングバブーン(Pelinobius muticus): 赤茶色の美しい体色を持つ、アフリカ最大のタランチュラ。
-
レッドバブーン(Harpactira pulchripes): 鮮やかな青い脚と金色の甲羅を持つ、人気の高いペット種です。
-
アースタイガー

Cyriopagopus minax
Photograph by Sarka Masova
アースタイガー(Earth tiger)は、アジアに広く分布するタランチュラのグループです。地表性や地中性の生活を送ることが多く、その名前は地中から獲物を狙う様子が虎のようであることに由来すると言われています。
-
特徴:
-
細く長い脚を持つ種が多く、動きが非常に素早いです。
-
刺激毛を持つ種と持たない種が存在します。
-
毒性が強い種が多いと推測されており、その獰猛な性格と素早さから、取り扱いには高い注意が必要です。
-
地表に穴を掘ったり、岩の隙間を隠れ家としたりして生活します。
-
-
代表的な種:
-
タイランドブラック(Cyriopagopus minax): 黒い体に毛がほとんどなく、光沢のある体表を持つ人気のペット種です。
-
コバルトブルー(Cyriopagopus lividus): 鮮やかなコバルトブルーの体色を持つ美しい種です。
-
タランチュラは他の生き物と共生する!?
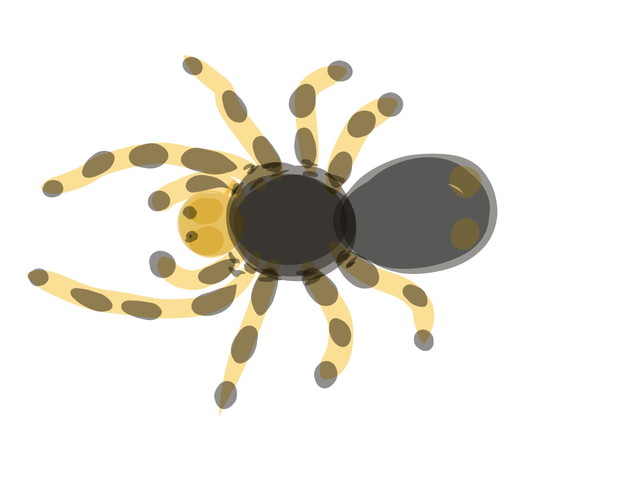
近年の研究でタランチュラが本来捕食対象であるはずの様々な生物と共生関係にあることが分かってきました。その中でも特に面白いカエルとアリとの共生関係について紹介していきます。
また、これ以外にもムチグモやヘビ、ザトウムシなどの生き物との共生も報告されています。
タランチュラとカエルの共生

ジムグリガエル科のカエル
研究によりジムグリガエル科のカエルに対しては攻撃を行わずに共生関係を築いていることが報告されています。
ジムグリガエル科のカエルの皮膚からは弱い毒性を持つ粘膜があるため、タランチュラは捕食対象にしないと考えられていますが、これだけではなく相互に以下のような利点があるため共生関係にあると考えられています。
-
タランチュラの利点:
-
カエルは、タランチュラの巣穴に侵入してくるアリや小型の昆虫を捕食します。これにより、タランチュラの卵や幼体を捕食しようとする外敵から巣穴を守る役割を果たします。
-
-
カエルの利点:
- カエルを捕食する小型の哺乳類やヘビなどはタランチュラにとっては捕食対象になり得るため、タランチュラの巣穴近くで生活することでそれらの外敵から身を守ることにつながります。
このような共生関係は、タランチュラが単なる獰猛な捕食者ではなく、複雑な生態系の中で他の生物と相互作用していることを示しています。
タランチュラとグンタイアリの共生

グンタイアリの一種
今までの調査で獰猛で攻撃的なグンタイアリがタランチュラの巣穴に入っていく様子が観察されてきました。
タランチュラもグンタイアリが巣穴に入ることに抵抗を示すことはなく、グンタイアリもタランチュラ自身や卵を襲うことはありません。それではなぜこのような光景が見られるのか、それは以下の利点がお互いにあるためと考えられています。
-
タランチュラの利点:
- タランチュラが捕食した食べかすをアリが食べてくれるので、巣穴の環境が保たれる。
-
グンタイアリの利点:
- 苦労することなく餌を定期的に手に入れることができる。
このような利点があるために、共生関係を築けていると考えられています。万が一グンタイアリがタランチュラを襲おうとしても、タランチュラの毛深い体毛に阻まれるため、このような防御機構も共生関係を築くための要素となっています。
タランチュラの毒
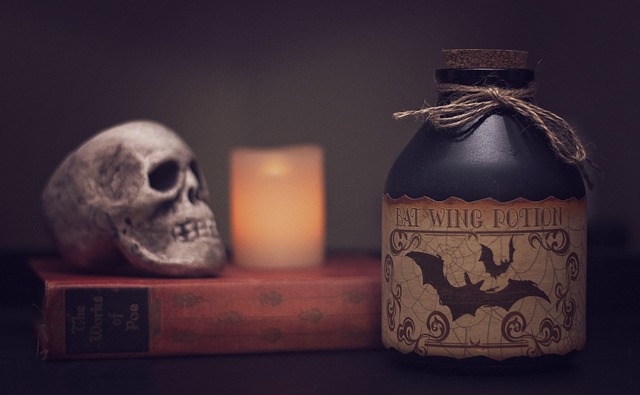
タランチュラの毒は、一般的に人間にとって致命的なものではありません。しかし、その毒性や症状は種によって大きく異なり、注意が必要です。
-
毒の成分と作用:
-
タランチュラの毒は、主に神経毒性と細胞毒性を持つタンパク質やペプチドで構成されています。
-
神経毒は、獲物の神経系に作用して麻痺や死に至らせます。
-
細胞毒は、獲物の組織を破壊し消化を助ける役割を持つと推測されます。
-
-
人間に対する毒性:
-
多くのタランチュラの毒は、人間が刺された場合、ハチに刺された程度の痛みや腫れ、発赤を引き起こす程度で重篤な全身症状は稀です。
-
しかし、中には毒性が強く激しい痛みや吐き気、発熱などの全身症状を引き起こす種も存在します。
-
アレルギー反応: 最も注意すべきは、毒液に含まれる成分に対するアレルギー反応です。過去にハチや他の昆虫に刺された経験がある人は、アナフィラキシーショックなどの重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
-
毒性の強さの推測: 一般的に地中性の種は比較的毒性が弱い傾向にあるのに対し、樹上性の種やアフリカ・アジアに生息する一部の種はより毒性が強いと推測されています。
-
-
毒以外の危険性:
-
タランチュラが持つもう一つの防御手段は、刺激毛です。この毛が目に入ったり、皮膚に付着したりすると、激しいかゆみや炎症を引き起こすことがあります。特に目に入った場合は、角膜に傷をつけ、視力低下などの深刻な事態につながる危険性があるため、注意が必要です。
-
まとめ
タランチュラは、オオツチグモ科に属する世界最大級のクモの総称で、その生息地や生態は非常に多様です。
地中、樹上、地表など様々な環境に適応し、それぞれツリースパイダー、バードイーター、バブーンスパイダー、アースタイガーなどのグループに分類されます。
一部の種では、タランチュラの巣を外敵から守るためにカエルやアリ、ヘビ、ザトウムシなどと共生関係を築くことが分かってきており、複雑な生態系の中で生活しています。
タランチュラの毒は一般的に人間にとって致命的ではありませんが、ハチに刺された程度の痛みや腫れを引き起こすことがあります。また、毒性には個体差や種差があり、特に樹上性やアジア・アフリカに生息する一部の種は毒性が強いと推測されています。
さらに、身を守るために飛ばす刺激毛が、皮膚のかゆみや炎症、目に入った場合は深刻な損傷を引き起こす危険性があるため、取り扱いには十分な注意が必要です。






コメント