ナイリクタイパンとは

Photograph by Cameron de Jong
ナイリクタイパンは、爬虫綱有鱗目コブラ科オーストラリアコブラ属に分類されるヘビで、学名は Oxyuranus microlepidotus と表記されます。その名の通り内陸部に生息し、陸上ヘビの中でも最も強い毒を持つことで知られています。
和名では「ナイリクタイパン」と呼ばれますが、英語では「Inland Taipan(インランドタイパン)」、または「Fierce Snake(フィアススネーク)」とも呼ばれます。「Fierce」という言葉は「獰猛な」という意味合いがありますが、実際には臆病な性格をしているため人を襲うことは稀であると言われています。

フードを持つキングコブラ
ナイリクタイパンは成体になると全長約1.8~2.5メートルに達する比較的大型のヘビで、鱗は小さく滑らかであり体全体が均一な色合いをしていることが多いですが、腹部は淡黄色をしています。
頭部はやや細長く、吻(ふん)は丸みを帯びています。目は比較的小さく、瞳は黒色です。他のコブラ科のヘビが持つことの多いフード(頸部を広げる構造)は持ちません。日中に活動することが多いですが、極端な暑さの際には朝夕に活動することもあります。
食性は肉食で主に小型哺乳類(特にネズミ類)に狙いを定めます。獲物を見つけると慎重に忍び寄ってから非常に素早く正確な攻撃を行い、獲物に複数回噛みついて強力な毒液を注入して弱らせ、死に至らしめたりしてから捕食します。
体色と季節による変化

Photograph by Cameron de Jong
一般的にはオリーブ色、黄褐色、濃い茶色など地味な色合いをしていますが、興味深いことにナイリクタイパンは、生息地域や季節によって体色に変化が見られるというおもしろい特徴があります。

Photograph by AllenMcC
冬のナイリクタイパン

Photograph by AllenMcC
夏のナイリクタイパン
涼しい冬の時期には体色がより濃い色合いになる傾向があります。これは、濃い体色がより多くの太陽光を吸収し、体温を維持するのに役立つと考えられています。一方、暑い夏の時期には、体色がより明るい色合いになることで、過度な体温上昇を防ぐ効果があると言われています。
このような体色の変化は、ナイリクタイパンが生息する乾燥した内陸部の厳しい環境に適応するための重要なメカニズムであると考えられていて、周囲の環境に溶け込むことで捕食者から身を守るカモフラージュの役割も果たしているとも考えられています。
分布と生息環境

Photograph by Taipan198
ナイリクタイパンの生息域
オーストラリアの内陸部の限られた地域にのみ分布している固有種で、具体的には、クイーンズランド州南西部、南オーストラリア州北東部、ニューサウスウェールズ州北西部の乾燥した地域に生息しています。
これらの地域は、降水量が少なく、乾燥した草原や低木林、岩場などが広がっていて、特に、ミッチェルグラス(Astrebla spp.)が生い茂るブラックソイル(肥沃な粘土質の土壌)の平原は、ナイリクタイパンにとって重要な生息地となっています。また、川沿いの低木地帯や岩の多い丘陵地帯にも生息することが確認されています。
人里離れた乾燥地帯に生息しているため人間との遭遇は比較的稀ですが、農地開発などによる生息地の破壊や、気候変動による生息環境の変化が、ナイリクタイパンの個体数に影響を与える可能性も指摘されています。
ナイリクタイパンの毒

Photograph by Jesse Campbell
ナイリクタイパンの毒は、その毒性の強さにおいて陸上ヘビ最強と言われており、その半致死量(LD50)は、皮下注射で0.025mg/kg程度と非常に低い数値を示しています。
用語解説
LD50(50%致死量、半致死量):Lethal Dose 50
ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。
ある一定の条件で動物にある物質(成分)を投与した場合に、動物の半数を死亡させる物質(成分)の量を示しています。LD50を使うことでその物質(成分)の毒性を比較することができます。一般的にはLD50 1500mg/kg以上の物質(成分)が安全とみなされています。
日本の毒ヘビの毒性と同条件で比較すると、ハブの1000倍以上、マムシの640倍、国内の陸上ヘビで最強のヤマカガシと比べても200倍以上の強さを誇るようにナイリクタイパンの毒性は桁違いの強さを示します。
内陸タイパンの毒は主にパラドキシン(PDX)、オキシレピトキシン-1、α-オキシトキシン1、α-スクトキシン1といった神経毒から構成されていますがそれ以外にも以下のような有毒成分が含まれています。
- 血液に影響を与える出血毒(凝血作用)や血管に影響を与える毒素
- 筋肉に影響を与えるミオトキシン
- 腎臓に影響を与える腎毒性物質
- 毒の吸収率を高めるヒアルロニダーゼ酵素
パラドキシン(PDX)は、これまでに発見されたβ神経毒の中で最も強力なものの一つであると考えられています。β神経毒は、神経終末から神経伝達物質アセチルコリンの放出を阻害します。
もしも噛まれてしまうと、幹部の痛み、頭痛、嘔吐、腹痛、めまい、虚脱、痙攣などの症状が現れて、その後主要な各種臓器に影響を与えることで腎不全や呼吸麻痺などを引き起こすことで最終的には死に至ります。また、アナフィラキシーショックを引き起こすことも知られています。
毒の量と致死量
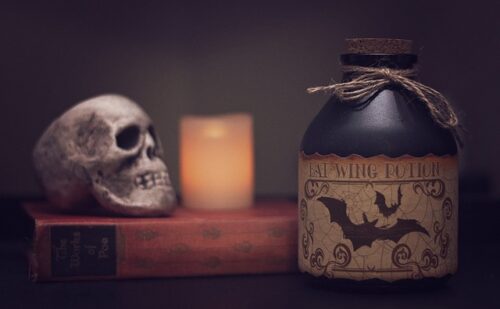
ナイリクタイパンの毒の平均量は44mgですが、最大量は110mgと記録されています。多いのか少ないのか分かりにくいかもしれませんが、実はコブラ科のヘビの中では比較的量は少ない部類に入ります。
コブラ科に属するインドコブラの毒量は平均169mgで最大610mg、北米のクサリヘビ科に属するヒガシダイヤガラガラヘビは平均410mgで最大848mgと比べるとその少なさが分かると思います。
ちなみにハブは特に毒量が多いことが知られていて、一咬みで300mg程度の毒を注入します。
このようにナイリクタイパンの毒量は少ないですが、半致死量(LD50)が0.025mg/kgという驚異的な毒性を持っているため、成人男性100人以上を死に至らしめることができるのです。
現地では驚異的な存在ではない?

その猛毒性から、ナイリクタイパンは非常に危険なヘビとして認識されていますが、実際には臆病な性格のため脅威を感じない限り積極的に人を襲うことはほとんどなく、多くの場合は逃げようとします。
過去には咬傷事故も報告されていますが、その頻度は他の毒蛇と比較して低いと言われています。これは、生息地が人里離れた乾燥地帯であることや、ナイリクタイパンの慎重な性格によるものと考えられます。しかし、もし噛まれてしまった場合には迅速な対処が不可欠です。
噛まれてしまったら?

ナイリクタイパンに噛まれる事故は稀ですが、万が一遭遇して噛まれてしまった場合には、迅速かつ適切な対処が非常に重要です。
もしも治療しなかった場合の致死率は80%近いとも言われますが、幸いにも血清が存在するため迅速かつ適切に対処すれば助かる可能性も上がります。
まずは落ち着いて動かないようにしましょう。 パニックになると心拍数が上がり、毒の体内への拡散を早めてしまう可能性があるため、落ち着いてできるだけ動かないようにしましょう。
周囲に人がいる場合はすぐに助けを求め、救急車を呼んでもらって噛まれた場所よりも心臓に近い部分を縛り安静にしておきます。すぐに医療機関を受診しましょう。
その際、どのようなヘビに噛まれたのかきちんと確認しておき、医者に伝えることで適切な対処を迅速に受けることができます。
まとめ
ナイリクタイパンはオーストラリア内陸部の乾燥地帯に棲む固有種で、陸上ヘビの中で最強の毒を持つことで知られるヘビです。その体色は、季節によって変化するという特徴を持ち、冬には濃い色で太陽光を吸収しやすく、夏には明るい色で体温上昇を抑えると考えられています。この体色の変化は、厳しい内陸の環境に適応した結果と言えるでしょう。
特筆すべきはその毒性で、LD50値は極めて低く100人の命を奪えるほどの猛毒です。主成分は神経毒であり、獲物の神経機能を麻痺させることで迅速に仕留めます。しかし、その凶暴なイメージとは異なり、実際には臆病な性格をしているため人間への被害はほとんどありません。
生態を知って適切な対処法を理解しておくことで、過度な恐怖心を抱くことなく、この凶悪な毒を持ったおもしろい生物と共存していくこともできるでしょう。







コメント